コラム事例紹介
【ARとオブジェクトVRの違いとは?】適材適所の活用ポイントを解説

こんにちは。コマーシャルスタジオKOOのamanoです。
近年、オンラインショップや展示会、製造業などさまざまな現場で注目を集めている「オブジェクトVR」や「AR(拡張現実)」といった3D技術。
どちらも商品や情報を立体的に見せることができ、体験価値の高いコンテンツとして活用が広がっています。
とはいえ、いざ導入を考えたときに
「オブジェクトVRとARって何が違うの?」「自分たちにはどちらが合っているのか?」
と迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、オブジェクトVRとARの違いをわかりやすく解説し、用途や目的別の活用ポイントをご紹介します。
オブジェクトVR撮影・制作ならテンサツにお任せ!
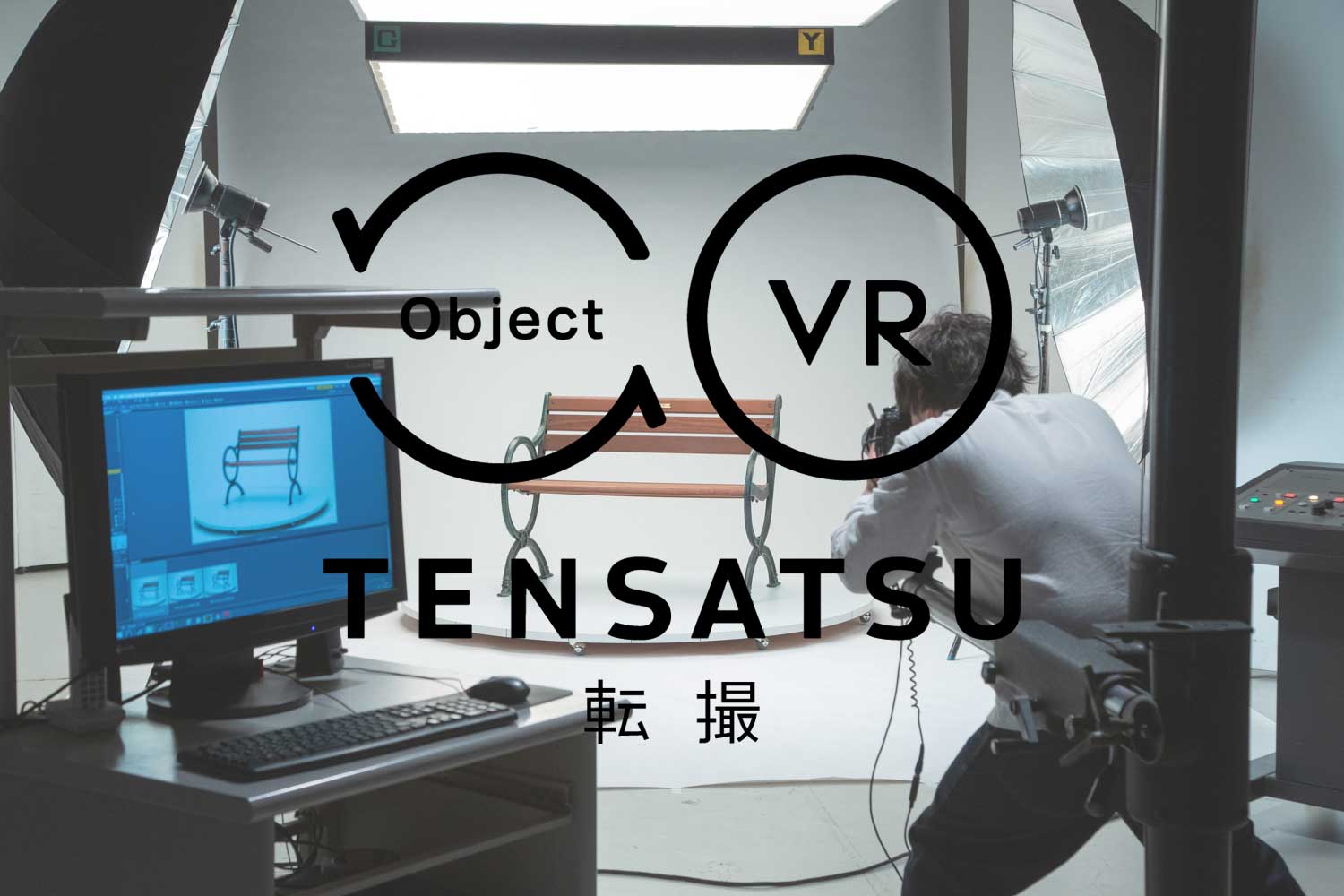
➡️ TENSATSUのお問い合わせはこちら
▶️ TENSATSUのサイトはこちら
VR、AR、オブジェクトVRの違いとは?
まずは基本的な定義と特徴から見ていきましょう。
VR(バーチャル・リアリティ)
VRは、「仮想現実」とも訳される技術で、ユーザーを完全に仮想空間へ没入させることを目的としています。
ヘッドセットを装着すると、視界のすべてがCGで構成された空間に切り替わり、現実世界とは切り離された体験が可能になります。
活用例としては、不動産のバーチャル内見や、ゲーム・エンタメコンテンツ、仮想ショールームなどがあります。
空間全体を再現したいケースや「その場にいる」ような感覚が必要な場面で力を発揮します。
AR(拡張現実)とは
AR(拡張現実)は「現実世界にデジタル情報を重ねる」技術です。
たとえば、スマホ越しに商品を映すと、その上に3Dモデルや説明が出てくるといった使い方が代表的です。
ARの特徴は、「現実を補足する」点にあります。
現場作業のナビゲーションや製造ラインでの指示表示、観光地の案内など、リアルな空間と連携しながら情報を加えるのに適しています。
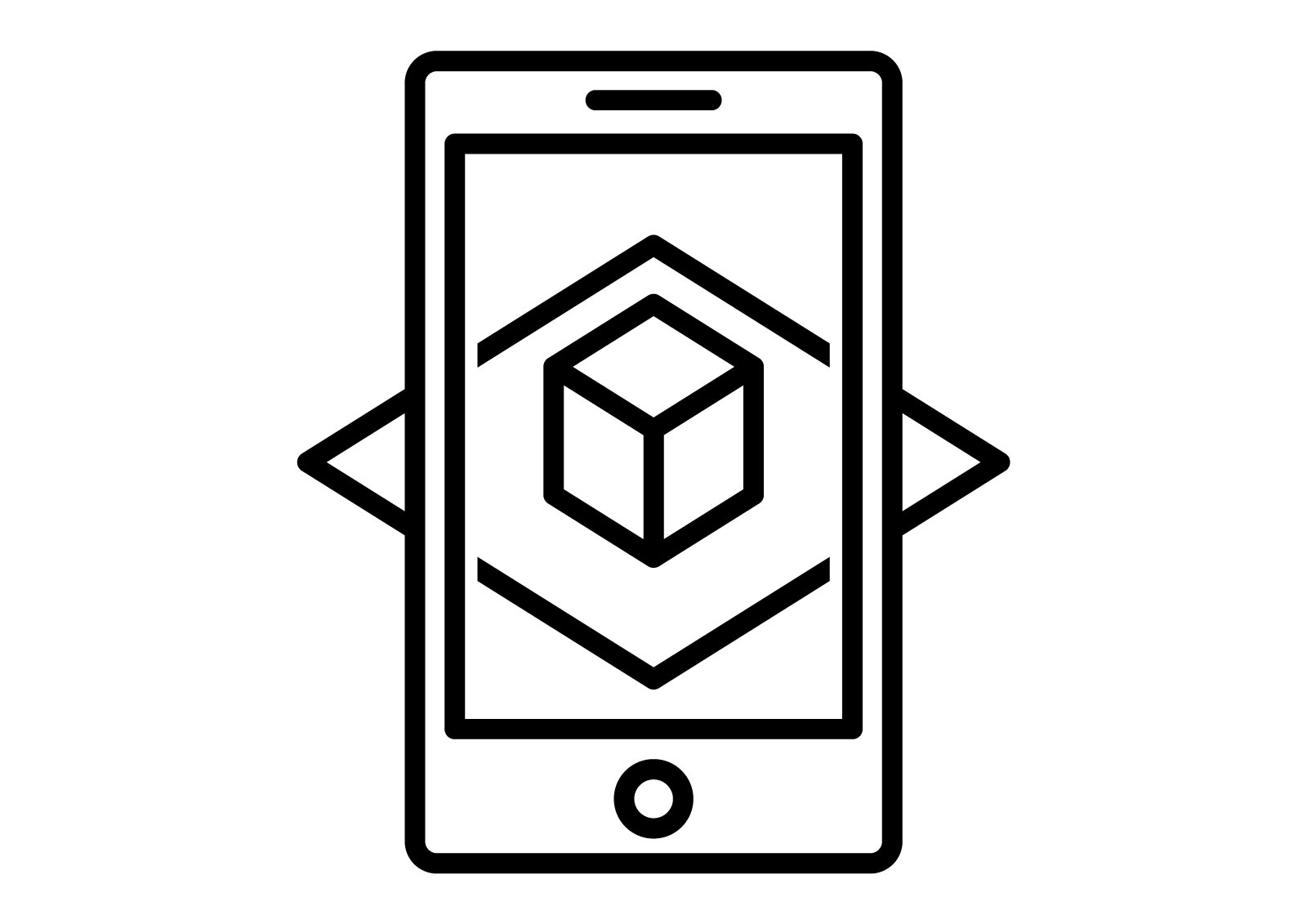
ObjectVR(オブジェクトVR)とは
オブジェクトVRは、現実の製品を360度・高精細に表示して、自由に回転・拡大縮小して閲覧できる技術です。
ユーザーはマウスやスマホの指操作で商品を「くるくる回しながら」確認でき、あたかも実物を手に取って眺めているかのような体験が得られます。
VRのような没入感や、ARのリアルタイム連携とは違い
Web上で誰でも簡単にアクセスできる手軽さと、商品理解の深さを両立できる点が特長です。

(自転車のオブジェクトVRはこちら)
オブジェクトVRとARの機能を比較してみよう

(指輪のオブジェクトVRはこちら)
オブジェクトVRは、あらかじめ商品をさまざまな角度から撮影し、
それをつなげてユーザーが自由に回転・拡大して見られるようにしたものです。
そのため、商品の質感や細部のつくりを丁寧に見せることに適しています。
例えば、ジュエリーや腕時計、靴など「手に取ったように見せたい商品」との相性は抜群です。
一方のARは、商品を空間に“置いてみる”ような体験が可能です。
スマホを通じて現実空間に商品を合成し
「この家具を自宅のリビングに置いたらどう見えるか」「この機械を工場に設置したらどうなるか」
といった空間との相性をシミュレーションすることができます。
つまり、オブジェクトVRは“細部を見る”体験、ARは“空間で試す”体験に適していると言えるでしょう。
用途別に見るおすすめの使い分け
ECサイトにはオブジェクトVRが最適
オンラインショッピングでは、ユーザーが実物を手に取って見ることができません。
オブジェクトVRを使えば、商品を360度自由に回転させて確認できるため、購入前の不安や疑問を減らしコンバージョン率アップにもつながります。
とくにアクセサリーやコスメ、靴など、細部の見た目が重要な商品には効果的です。
「写真ではわからなかったけど、回して見たら納得して買えた」といった購入者の声もよく聞かれます。

(時計のオブジェクトVRはこちら)
展示会やショールームではARが便利
限られた展示スペースでたくさんの商品を紹介したいときは、ARが強い味方になります。
タブレットやスマホを使って、来場者が自由に商品を空間に配置して見られるようにすれば
実物を持ち込まずに豊富なラインナップを紹介できます。家具、家電、建材など大型商品との相性も◎。
また、複数のバリエーションをその場で切り替えて比較できるのもARならではの強みです。

教育や製造の現場では両方を組み合わせても◎
構造が複雑な機械や製品の使い方を説明したいとき、オブジェクトVRで構造を可視化し
ARで実際の操作手順を重ねて見せることで、理解度を高められます。
たとえば、新入社員向けの研修や技術者への操作マニュアルなどに活用できます。
費用感と導入のハードルの違い
オブジェクトVRは、基本的に撮影とデータ作成のみで完結します。
対応もWebブラウザ上でできるため、サイトに埋め込むだけで簡単に導入可能。
撮影費用も数万円からと比較的手軽に始められるのが魅力です。
一方、ARは商品データの3D化に加え
ユーザーのスマホや空間認識機能への対応、場合によっては専用アプリの開発が必要になることも。
その分、体験のインパクトは大きいですが、費用も数十万〜数百万円と大きくなるケースもあります。
「まずは低コストで試してみたい」「すぐにサイトに導入したい」という方には、オブジェクトVRの方が現実的かもしれません。
目的に応じて正しく選ぼう!
オブジェクトVRとAR、どちらも魅力的な3D表現ですが、得意なこと・向いている場面が異なります。
・商品を細かく見せたいなら「オブジェクトVR」
・空間に商品を置いて体験させたいなら「AR」
と覚えておけば、活用の方向性がぐっと明確になるはずです。
オブジェクトVR撮影・制作ならテンサツにお任せ!

テンサツでは、商品に最適な撮影・表現手法をご提案し、効果的な導入をサポートしています。
「うちの商品にはどちらが合う?」「具体的な導入方法が知りたい」など、気になることがあればお気軽にご相談ください。
➡️TENSATSUのお問い合わせはこちら
▶️TENSATSUのサイトはこちら
▶️ECサイトでのオブジェクトVRの使用例はこちら
くるっと360°回転できる
オブジェクトVR撮影・制作
ワンストップサービス
家具・人物・車・宝石・美術品・精密機器など大型商品から小型商品まで、
高精細オブジェクトVR撮影&制作サービスです。
360度撮影
Photo shooting

オブジェクトVRのための高精細360度ライティング撮影をします。弊社のオブジェクトVR撮影専用スタジオでの撮影、または出張での撮影も承ります。
オブジェクトVR制作
Object VR
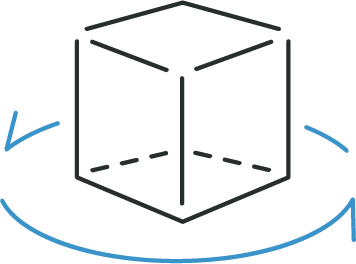
撮影した写真にてオブジェクトVRを生成します。弊社サーバーのご利用も可能ですので、貴社サイトにiframeタグを埋め込むだけで使用することもできます。
ご依頼・お問い合わせはこちら
(スタジオKOO)


